ふつうに生きていたら転落する。
講談社現代新書公式より
知識社会化が進み、人生の難易度がますます上がっていくーー。
残酷な「無理ゲー社会」を攻略するための
たった一つの生存戦略とは?
才能のある者は人生を攻略(HACK)し、
才能のない者はシステムに搾取(HACK)される。
常識やルールの「裏道を行け」!
私が個人的に、大好きな作家の最新の本です。
橘玲さんは、ブログテーマで掲げている『経済的自由の羅針盤』が必要な事を教えてくれた作家です。
『裏道を行け ディストピア世界をHACKする』を読むと、現実の無理ゲー社会を攻略するHACK本なのか?
というとそういう本ではありません。
しかし、こちらを読むと現代がいかに無理ゲー社会なのか?を事例やデータをもって解説されているので、学ぶことが出来ます。
そして、それをHACKする為のヒントを得ることができるものだと考えます。
今回学んだ事
価値の変換が起こっている現在、情報を発信し、自分というものを認めてもらう事が重要。SNS社会での生き方を自分なりに見つける事。依存せず、一定の距離を保つことも重要。
では、本書はどういった構成になっているのかと言うと、下記の構成です。
PART1 恋愛をHACKせよーー「モテ格差」という残酷な現実
講談社現代新書公式より
PART2 金融市場をHACKせよーー効率よく大金持ちになる「究極の方法」
PART3 脳をHACKせよーーあなたも簡単に「依存症」になる
PART4 自分をHACKせよーーテクノロジーが実現する「至高の自己啓発」
PART5 世界をHACKせよーーどうしたら「残酷な現実」を生き抜けるか?
PART1 恋愛をHACKせよ
自由恋愛になり、恋愛にも格差が生まれていること、それを恋愛工学というテクニックで攻略する事例がまとまっています。
この章では、恋愛工学の話が多く、女性目線というよりは、男性による恋愛HACKの話となっているので、女性目線で見た恋愛HACKのお話はありません。
ただ、こういった事例や歴史があったと言う事から、性別問わず、恋愛工学を知るという点では学びがあると思います。
ただ、淡々と事例をもとに解説されるので、感情的に受け入れられない人もいるのかなと思います。
PART2 金融市場をHACKせよ
投資の世界において、儲けるためにはどうすればいいか?
ここでは、様々な事例が紹介されていますが、凡人が株式市場で儲けるなら、長期投資でインデックスファンドでコツコツやることが、大事なのかなと改めて思いました。
人間心理からくる市場の歪みを見つけた時に、稼ぐ可能性があるもの理解できました。
しかし、資金面や市場を見続ける力が必要と考えると、個人で穴を突いた投資をするのは、なかなかハードルが高いなとも思いました。
金融市場の稼ぎ方の変遷や、思惑が学べて面白いです。
PART3 脳をHACKせよ
ここでは、人が依存症になる事例が複数紹介されています。
そして、SNSがなぜ人を依存させるのかも学べます。
考えてみれば、SNSを作成している企業は、いかに多くの人に使ってもらうかという事を日々考え、改善しています。
そして、それを行う為に、高額な報酬で多くの優秀な人材を雇っているわけです。
凡人がそれにあがらうには、なかなか難しいものがあるなと思います。
PART4 自分をHACKせよ
この章では、ほんとうの自分探しという精神的な話の部分と、テクノロジーの進化による人間の拡張の話が実例をもとに説明されています。
去年完結した、新世紀エヴァンゲリオンの話が冒頭から出てきたりして面白かったです。
この章を読んで思ったのは、テクノロジーの進化による人間の拡張が、一部普通になってきているという事です。
自分が知っている事例でいえば、例えば、白内障の手術時に視力の矯正も一緒に行うことが可能になってきていたり、
パワードスーツが開発され、重い荷物を楽に運べたりできるようになった事。
技術的な発展が、人間の老化や能力支援が現実的になってきているという事。
さらには、マイクロチップの埋め込みにより、鍵の開け閉めや電子決済まで可能になるという時代。
ひょっとすると攻殻機動隊のような世界は、そんなに未来の話ではないのかもしれないと思いました。
PART5 世界をHACKせよ
最終章では、現在起こっている世界の変化の話から、世界が今後どのように変わっていくかという作者の疑問で終わります。
この章を読んで思ったのは、生きづらいと感じているのは、日本人だけでなく、世界的な潮流である事。
グローバリズムから変わる次のパラダイムシフトが起こる可能性がある事。
今後の世界を考える場合、自国という小さなポイントで考えるのではなく、世界はどのように変わっているのかも考えざるを得ない事。
そんな時代に生きているからこそ、みんなが無理ゲー社会になったと感じるのかなと思いました。

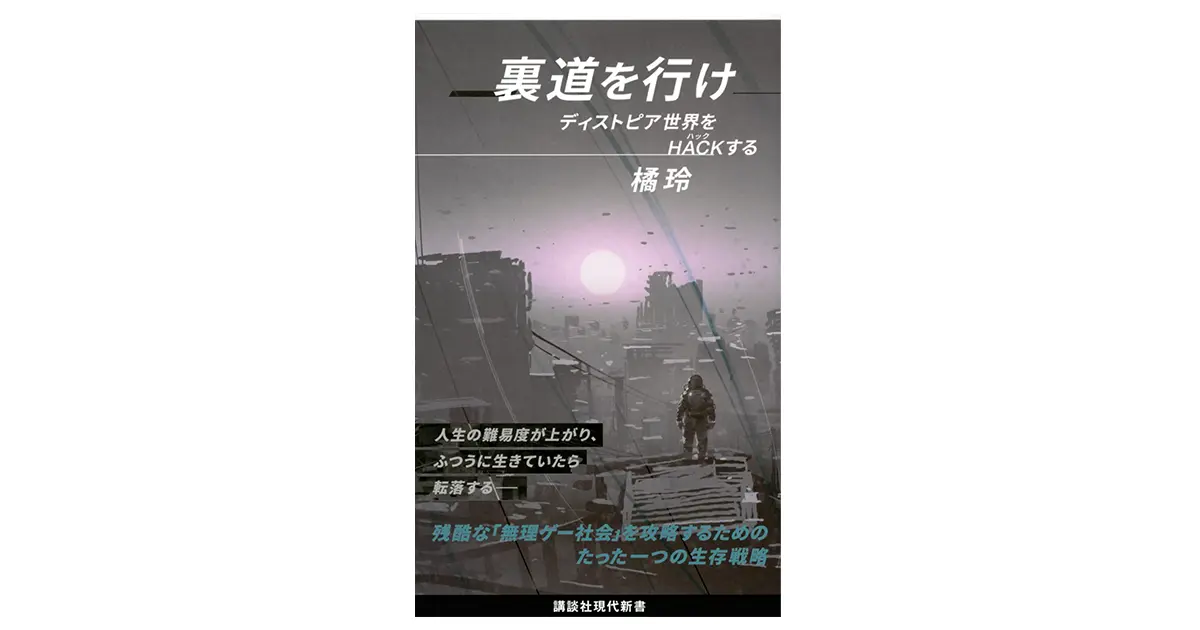


コメント